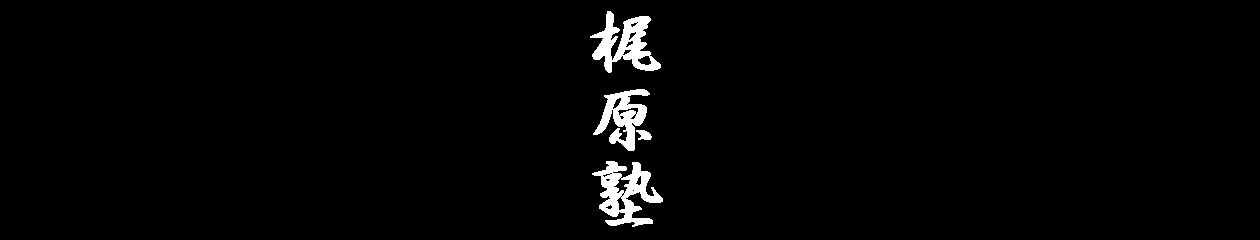中学校では期末テストが終わり、高校生は中間が終わって期末テストが始まるころです。
中学生のテスト前の約2週間の勉強時間を見てみました。
だいたいの時間ですが、一番勉強した生徒と、勉強していない生徒を見てみましょう。
一番勉強した生徒(3年生) 60時間前後(去年も60時間ぐらい)
一番勉強していない生徒(1、2年生) 15時間前後
4倍ぐらい違うのですが、今までは80時間ぐらい勉強する生徒が多くいました。
受験生優先なので、1年生は少し早めに帰宅してもらっていました。
中3の受験生は受験まであと8か月を切っています。
『もっと勉強しておけば良かったなぁ』と思うことは普通です。
塾長だってそう思いました。
時間はみなさんに平等にあたえられています。自分の勉強時間をたしかめてみてください。
成績が上がらなかったら、もっと勉強しないといけないということです。勉強方法を見直すなどは量を増やした次に考えることです。
『勉強している時間』を増(ふ)やさなければ、学力は上がりません。
勉強している時間とは、授業を聞いている時間ではなく、ましてやボーっとしている時間ではありません。自分で考えていたり覚(おぼ)えたりしている時間です。
宿題は勉強ではありません。作業(Do)です。『宿題をする(Do homework』であり、『宿題を勉強する』とは言いません。
勉強は質も量も必要です。まずは量を増やすことです。無駄を経験しないとわからないことがあります。最初から効率よく勉強はできません。
1年生は初めての定期テストの結果が出ました。残念ながらテスト結果というのは塾長の予想を大きく超えることはあまりありません。ここで気づいてほしいことは、指示通りにやらなかった結果どうなったかです。スポーツも勉強も同じで、まずは指導者の指示通りやってみる。そこから自分で工夫するのです。
今日も昨日と同じか?
============================
生きる力
国は子供たちの教育に生きる力を求めている。
というのは、覚えることばかりの勉強から、自分で考えて問題を解決していく勉強へと変わっていったのだ。
たしかに今の子供たちは問題を解決する方法や人と話し合う方法を知っているように思う。
しかしだ、『生きる力』はあるのだろうか。その答えが出るのは数十年先だろう。
『コンプライアンス』という言葉は聞いたことがあるだろう。法律を守るということだ。
昔は、親はもちろん、学校の先生から怒られるなんてのは当たり前で、近所のおじさんや知らない大人からも怒られた。
今は、親ですら怒ることができないようになってきている。ということは、自分で自分を厳しくするしかないのだ。これは、非常に難しい。
自分に打ち勝つことが、最も偉大な勝利である
プラトン(哲学者)