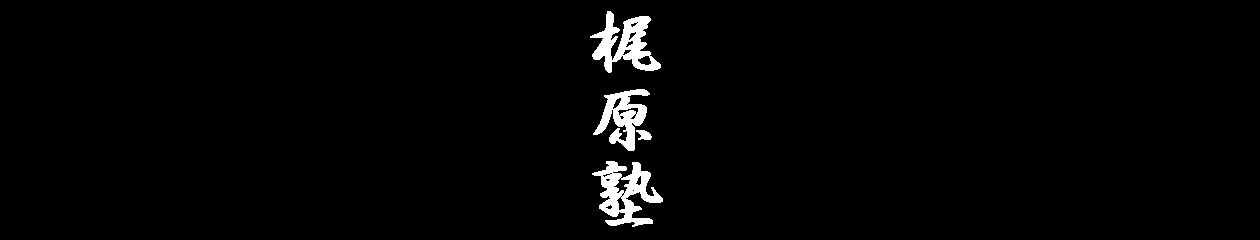大学入試の共通テストは来月に、公立高校の入試はあと2か月を切りました。
受験生はこの時期に何をやるべきなのか、短い期間ですので意識を持ちましょう。
中3生は成績も決まって受験勉強を残すのみです。
学校で過去問を買った人もいると思いますが、焦って過去問を始めてはいけません。
※毎年注意喚起していますが、それでも過去問に手を出す人がいます。
この時期は基礎を見直すことと3年生の残りの学習を終わらせることです。
基礎を見直すことにより、やらなくてもいいところを決めます。
捨てる問題を作ることも必要です。
今までの3年弱の学習をわずか2か月で復習するわけです。ちょっと勉強したぐらいでどうにかなると思わないほうがいいです。
それよりも、絶対に取れる問題を確実にしましょう。
点数は伸びないのが普通であって、安定した点数が取れることが重要になってきます。
難しいことや計画は塾長が考えて伝えます。
それと、やってほしくないことはあります。
・新しい問題集をやりはじめる
・友達と勉強
問題集は塾にあります。十分にそろっていますので買う必要はありません。
教科書や資料集は持っているはずです。それで十分です。覚えるまで読みましょう。
友達と勉強したところで、足の引っ張り合いになることがほとんどです。
やるべきことをしっかりやりましょう。
塾長はカーナビ、みなさんは運転手です。ナビ通りに進まなければ目的地にたどり着きません。
これから受験当日までに一番気を付けてほしいところは体調管理です。
一日一日が重く感じてきますので、勉強よりも気を使ってください。また、緊張感をもっていきましょう。
クリスマスや正月、人が集まることが多くなってきますが、受験までは我慢しましょう。
若い時に人の基礎は作られる。なんでも同じです。
今日も昨日と同じか?
============================
それぞれのあゆみ
年金の3階建てというのがあった。ざっくりいうと、公務員の年金は会社員の年金に公務員の独自の年金が上乗せされる仕組み(3階部分)があった。この3階部分が払い終わるのが塾長の年齢ぐらい。
だから同級生は退職して新しいことを始めたりするらしい。
そんな話を同級生と話していたのだが、それぞれ残りの人生をどう生きるかを考え始めていた。
居合道の忘年会に行ってきた。周りのおじさんたちがどんどん6段や7段に合格して偉くなってきたので、塾長は取り残された感じはある。年齢が周りに比べると若いというだけが救いだ。
『早く6段に合格しろ』と叱咤激励されたが、どうにもやる気が上がらない。
年末に向けて来年の抱負を考えるが、居合をどうするかが悩みどころだ
笑われて笑われて強くなる
太宰 治(作家)